「俺のTジョイ久留米」で 『GANTZ』。
どうやら俺のTジョイ久留米は「二宮&松ケン召喚キャンペーン」でTOP100に入賞したらしく、劇場のロビーに手形つきポスターが展示されていた。「TOP100」とか漏れる方が難しいと思うけど。
「二宮の手、ちっちぇ~な~!」と思って、自分の手を重ねたら全く同じ大きさでした。
で、今回の「GANTZ」なんですが。
原作漫画の徹底的なエログロ描写、膨大な情報量の物語、現時点で30巻も出てるっていう長さ、しかも未完。
これを実写化ってどうやんの? と。
どの程度忠実に映画化して、どの程度改変してくるのかっていうのが、観る前の印象だった訳ですけど。
なんせ前後篇PART1・PART2の2部構成なんでね、まだ物語の全容も分かんない段階なんでなかなか語りにくい部分もあるんですけど。
前編だけ見て「この描写が足りない」「ここは余計だ」って思ったとしても、それには意味があって、それが後半で何らかの物語に繋がってて「ああ、それでか!」って事もありえますからね。
で、まあ、正直そんなに期待してなかったんですよ。半笑いで観に行った感じだったんですけど・・・。
結論から言うと、合格は合格だと思います!ごうかく~!
っていうか、これぐらい出来てるんだったら合格って言ってあげないと、これから先こういう映画(スケールの大きい漫画実写化の映画)は作れない。
原作では主人公玄野は中学生って設定なんだけど、今回の映画では大学生。就職活動真っ只中っていう設定になってるんですね。
まず映画が始まって、冒頭、駅のホームで主人公・玄野が電車を待ってる。ここは原作通り。
玄野は電車を待ってる間「面接に受かる方法」「面接攻略本」みたいなのを読んでるんですよ。
しかも何故か、はっきりと声に出して読んでる。
映画で登場人物が読書したり手紙読んだりするって時は、人物が書いてある文字を目で追ってるところだけ映して、書いてある内容は「ナレーションで処理する」あるいは「書いてある文章をそのまま映す」ってのが普通だと思うんですけど、この映画だと二宮君はハッキリ口を開けて声に出して音読してるんですよね。
駅のホームで本を音読してる奴がいたら、それは基地の中に入れてもらえない人・基地の外にいる人ですよ。
これならまだ駅のホームで二宮君がスープDEおこげ喰ってる方がまだ良かったですよ。
始まって30秒でいきなりガックシですよ、ああ俺の半笑い姿勢は間違ってなかったと。
ところがね、このGANTZ、このあと急激に盛り返していくんですよ。
ガックシうなだれた僕の背筋がピーンとなってくる。
♪ランランラン、ランドセルは~ せすじ、ぴーん!ですよ。
何で盛り返していくのか?
こないだの「SPACE BATTLESHIPヤマト」にしろ今回の「GANTZ」にしろ、SFマンガの実写化でポイントとなるのは「映像的に(画ヅラ的に)どれくらい再現出来てるのか?」ってトコ。
この点においては非常に良い出来だったと思います。素晴らしい再現ぶりです。「漫画ヴィジュアルの実写再現」という面では100点満点差し上げてもよろしくってよ!
よくぞここまで頑張ってくれたと。
しかも「SPACE BATTLESHIP ヤマト」のような『ハリウッドの猿真似』ではない、日本ならではのSF表現になってるのも好感が持てます。今まで見た事ないSF表現・他のどの映画にも似てない世界観を味わう事が出来る、ハイクオリティな映像でした。
まず最初に「あ、これ、結構イイんじゃね?面白くなるんじゃね?」「これはイイ映画の予感がする!」って思ったのは、前半のねぎ星人との戦いのパートですね。
まずロケーションが素晴らしい。原作通り住宅地で戦うんですけど、もう、ほぼ全く漫画と同じ場所って言ってイイくらいの場所だと思います。
主人公達が戦闘場所へ転送され、この住宅地が映った瞬間、「は!これはイイ予感!」って思ったぐらい。
で、ネギ星人の再現度の高さも、ちょっとただ事じゃないレベル。
子供の体に大人の顔をCG合成したみたいですが、このクオリティには感心しました。
調べてみたところ、
顔はお笑いコンビ「フライングマン」の五十嵐翔さん(左)。
体は子役の早川恭崇くんだそうです。
「ベンジャミンバトン」の『見た目老人なのに体のサイズは子供』なアレを初めて見た時の衝撃を思い出しました。多分実際にベンジャミンバトンと同じ撮り方(同じCGのコンピューターシステム)だと思うんですけどね。ねぎ星人のキャスティング見たら2人の名前がクレジットされてましたし。
あの声にも心掴まれましたね。「ねぎあげます、ねぎあげます」っていう。
ちなみに原作版でのねぎ星人の口癖「ねぎだけでじゅうぶんですよ・・・。」の元ネタはブレードランナーの「2つで充分ですよ!」
(1:00頃)
ねぎ星人に限らず、他の星人のビジュアルや動き・演出も完璧だと思います。
で、ねぎ星人パートの一番の見所はやっぱり、子供のねぎ星人が殺されてからの流れ。要するにゴア描写満載のスプラッターシーンだと思うんですけど、このシーンのポイントは、事が起こる「場所」ですよね。
子供のねぎ星人がド派手に殺される→それを見つけた親ねぎ星人が逆上→親ねぎ星人によるド派手な復讐 ・・・っていう流れですけど、原作だとこれらの出来事って全部路上で起こるんですよね。
でも映画だと、民家の狭いガレージで起こるわけですよ。
一連の残虐シーンを狭い場所でやることによって緊迫感も出るし、大量の血飛沫が壁一面に飛び散ってコンクリートの白い壁が真っ赤に染まる事でより映像としての恐怖感が出る。
のっぴきならねえスプラッター感が出るんですよね。
で、ガレージっていう狭い場所、しかも「出入口が1か所しかない場所」だからこそ生まれる展開もあるわけです。
出入り口が1か所しかない狭い場所、つまり逃げ場がない場所を使う事で、さっきまで子供ねぎ星人を追いつめていた側の人間達が、瞬時に、一転して「追いつめられる側」になっちゃう。
ガレージで子供ねぎ星人が殺された後、ガレージの入り口に親ねぎ星人を立たせるだけで、人間側と星人側の立場が瞬時に逆転するっていう面白さも生まれてますね。
ここは上手いなと思いました。
あばれんぼう星人戦の二宮君の斜に構えた演技も良かった。
「星人は俺が1人で倒しといてやるから他の奴らはさがってろよ」っていう、その態度!
Xガンをギョイーン!とぶっ放して、その後ガン片手にちょっとプラーンとけだるい動きするとことか、あの態度、あの動き1発で主人公玄野のスタンスを表してて凄く良かった。
スプラッター描写グロテスク描写に関しては、まあ原作に比べりゃパンチは弱いかもしれないですけど、まあ色んな状況を鑑みても、あそこまでやれれば充分じゃないですかね。
PG12っていう年齢制限の中でやれるギリギリ限界のところまで頑張ってたと思います。
本気で原作通りのグロ描写やっちゃうとR18になっちゃうし、R18になっちゃうと予算もつかないし、予算付かないとGANTZなんてビッグバジェット映画は撮れないでしょうしね。
映像としての作り、ディティール・細部にいたるまで、すごく丁寧。
あのガンツスーツ。これも素晴らしい出来栄えですね。
竹田 団吾っていう劇団新幹線の衣装デザイナーの人がデザインやってるんですけど、この人は実写版ヤッターマンの衣装デザインを手掛けてたり、ここ数年の仮面ライダー映画シリーズ(ファイズ以降)ずっと衣装デザインで関わってる人。
このガンツスーツが、よく見ると男女でデザインがちがうんですね。女性用の方が体のラインが綺麗にでるような作りになってる。
という風に、ビジュアルやディティールはほぼ完璧なんです。
完璧なんですけど・・・これらの完璧なビジュアルを物語の中に全然活かせてない。物語の中に全然組み込めてない。
どうしてか。見せ方が下手糞だからです。。。
女性用の方が体のラインが綺麗にでるような作りになってるんだから、もうちょっとその辺見せてくれても良かったんじゃん?
何のために峰不二子体型の夏菜を大抜擢したのか?って事ですよね。
もっといえば、最初に夏菜がガンツ部屋に転送されてくるとき、"ちょうどいい"部分までしか見えないんですよね。
なんだよ見せねえのかよー。
子犬みたいな顔しやがってー。
いくらPG12とはいえ、エロが足りな過ぎやしませんか!
グロはまあこんなもんかなーって思いますけど(それでも原作に比べたら足りないけど)、エロは明らかに足りないでしょ。
GANTZにとって「エロティシズム」「フェチシズム」って凄く重要な要素ですよね。
特に原作の最初の方なんか、エロが玄野の起動力・原動力だったりもしますからね。ただ単に見た目っていう事もそうだし、物語的にもエロは重要な要素だと。
で、「見せ方が下手糞」って事で言えば・・・アクションシーンの撮り方が異様に下手。
登場人物が敵に向かって銃は構えるんですけどなかなか撃たない。
これホントイライラします。いいから撃てよ!っていう。
星人って呼ばれるクリーチャ―どもを倒すことで物語が進行する訳ですから、バトルシーンやアクションシーンはこの映画の最重要ポイントですよ。だから、もうすこしちゃんと見せなきゃねえ。
しかも、ねぎ星人の時はまだ良い方で、かろうじて観れるレベルだったんですけど、物語が進行していくにつれてどんどんアクションシーンが雑になっていきます。
終盤の千手観音とのバトルシーンなんかは特に雑なんですよ。
作り手がどんだけ分かっててやってるのか知らないですけど、暗くてよく見えないんですよね。
一応、夜の東京国立博物館って設定なんですけどね、それにしたって暗過ぎだろ。何が起こってるか見えないレベルで暗いっていうのは、もうこれは「誤魔化した」「逃げた」としか言いようがないですよ。
松ケンが刀を持って千手観音と戦う場面もねえ・・・。
松ケンが最初は正面から剣を突き刺されたのに、次のシーンでは背中側に剣が刺さってるっていうのもどうなってるのか分かんないし。
田中星人とのバトルシーンで、夏菜演じる岸本恵が鉄パイプで田中星人をぶんなぐるシーンあるんですけど、最初の2発ぐらいは敵が吹っ飛ぶぐらいの勢いでバコーンってぶん殴ってたのに、それ以降なぜか急に弱くなってポカスカポカスカになっちゃうっていう、そこら辺もよく分かんなかったです。
主要キャラでさえ無残に殺されていく所とか、女の子キャラが豪快にアクションする所とか描きたかったんでしょうけど、アクションシーンの流れをそこに持って行くのが異様に下手ですよね。
で、そんなバトルシーンなんですけど、ここでも日本映画最大の難点が登場しました。
それは「一刻を争う緊急事態に感傷的な独白シーンが続き、その間、時間が止まっている」という点。
どういうことかというと、
これも千手観音とのバトルシーンでの話ですが、仲間が殺された際あるいは仲間が命にかかわる傷を負った際に、いちいち愁嘆場を挟み込んで「大丈夫か!しっかりしろ!死ぬな!」みたいな、感傷的な切ないセリフのやりとりが延々と続くんですね。
Q: で、そのあいだ敵は何してるのか?
A:セリフのやりとりが終わるのをずっと待ってあげてる。
ダラダラと玄野と加藤のセリフのやりとりが続いてる間、敵の千手観音は『ちっ、もう~まだかな~?もう、早くしてよね~。』って待ってる状態なのか?っていうね。
しかもこういうクドクドした愁嘆場がこの千手観音戦だけで2回もあります。誰が死んだとかは一応言わないでおきますけど。
特にに2回目のクドさったらないですよ。
原作にはこういうシーンは一切ありませんから、わざわざ余計に足してるんですね。さすが日本映画としか言いようがない。
で、千手観音戦って事で言えば、二宮くん、途中から急に足治りすぎ。
さっきの仮病?っていうくらいピンピンしだすんですよね。
要するにさ~、脚本がさ~、結構さ~、クソの部類なんですよね~。
まあ、冒頭に「物語のハショり方、簡素化は比較的上手い」って言ったんだけど、せっかく上手に省略した部分に、明らかに不必要な要素を足してるんですね。
そんな要らない要素をわざわざ足すくらいなら原作削るなよ!って思っちゃいますよね。
脚本上の酷い部分は他にもありました。例えば二宮君のセリフ。
「人間には誰しも役割があります。云々かんぬん・・・」
っていうセリフを要所要所で何度も繰り返すんですよね。
これがホントにクドイ!
物語のテーマだったり映画全体のキーワードになるような事をセリフで言うっていうのもダメだし、それを何回も繰り返すっていうのは更にダメです。
「はーい、映画を御覧の皆さん、これが伏線ですよ~。」って、どんだけ観客がバカだと思ってるのか知らないですけど。
しかも「人間には誰しも役割があります」って、「ナンバーワンよりオンリーワンってか!?」っていう。
なーんか後編で唐突に「世界に一つだけの・・・」みたいな方向に話を持って行くんじゃないかっていう、悪い予感がしますよ。GANTZにそのテーマはぬる過ぎるだろ、と。
そして中盤の吉高ちゃんとの恋愛パートの生ぬるさは筆舌に尽くしがたいものがありましたね。
あの駅のホームの告白シーンの流れとか観てて恥ずかしかったなあ~。ホント邦画にありがちなこの手の幼稚なメロドラマ展開はどうにかならんのかね?
あと謎なのが田口トモロヲがいる理由ですよね。なにひとつ物語に関わってこないっていう。
まあこの辺は後編でどうなるかにもよる部分。後編でも同じような存在感だったらそれはそれで面白いですけどね。
そんでね、、、
前編・後編って作りとはいえ、あまりにも隠されてる部分・謎なままの部分が多すぎるんじゃないかと。
この謎は後編で明らかにされるんでしょうけど、それにしたって1本の映画としては何にも分かんなすぎるし、消化不良すぎるでしょ。
あまりにも謎が多すぎて、何に対して「これはどういうこと?」って思って良いのかも分からなくなってくる。
この映画のすべてが「後編を観るための予習映像」のような作りで、
「後編のために作った前編」という印象。
2時間半におよぶ壮大な予告編って感じです。
「前編を見たら続きが気になってしょうが無いから後編を観に行く」というよりは「後編を観るために前編を観とじかなきゃいけないという義務感で観ておく」っていう作りで、本末転倒というか、あまり健全な形じゃないと思います。
ほんでもってラストシーン、国立博物館に人だかりが出来てるって場面。
雨が降ってるんですが、集まった人だかり全員が全く同じ黒い傘。そんなことがあるか!
で、そこに現れた山田孝之1人だけ透明のビニール傘。そんなことがあるか!
結論から言うと、すごくイイ部分もある。すごく悪い部分もある。
ただ、映画の善し悪しは作品の出来によらないと思うんです。
ここが下手、あそこが足りない、そういうのはあっても良いんです。
作り手が「ここだけはもう超気合いを入れて作ったところだ!」「ここだけは絶対に観客の心を掴んでみせる!」っていう場面があるかどうかですよね。
映画自体の出来は多少悪くても、観客がグッと心を掴まれるような所があればそれでイイんじゃないかっていう。
だから、そういう見方で言えば、このGANTZって映画には「完璧なビジュアルの再現」や「今まで無かったSF表現」っていう心を掴まれる場面がありましたからね。
だから悪い所も色々あるけど「この映画はダメだ!」と言えない魅力があります。
だから前編だけ観た感じだけで言えば、どちらかというとイイ部分が勝ってるのかな?
っていう、やじろべえがグラグラしてる状態。
どちらかといえば「イイ映画」側に傾いてるかなって感じですかね。
ホントPART2次第って感じですね。







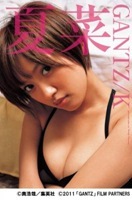



0 件のコメント:
コメントを投稿